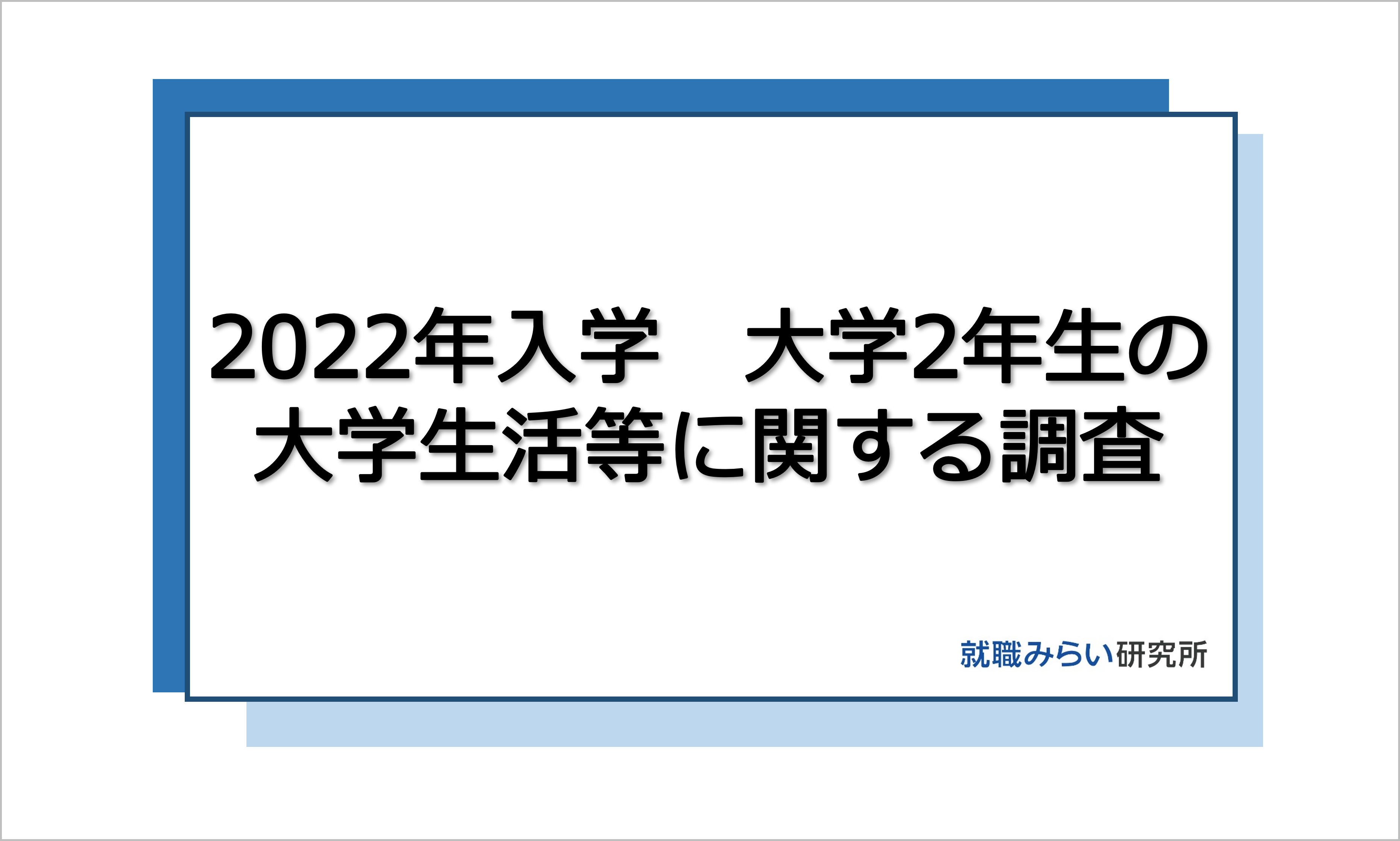各界の著名人に、これまでに出会った、プロとしてすごいと思った人、影響を受けた人など「こんな人と一緒に働きたい!」と思う人物像をインタビュー。
成長しようと頑張っている人たちが周りにいると、力をもらえる

せと・こうじ●1988年、福岡県生まれ。2005年、デビュー。以来、舞台やドラマ、映画と幅広く活躍している。近年の出演作に舞台『ドクター・ホフマンのサナトリウム~カフカ第4の長編~』『関数ドミノ』、映画『寝ても覚めても』など。ドラマ出演も数多く、NHK連続テレビ小説『まんぷく』、『ルパンの娘』などがある。2020年4月スタートのTBS系火曜ドラマ『私の家政夫ナギサさん』では、主人公・相原メイの仕事上のライバル「田所優太」を演じる。
デビュー後6年間は、誰とも深くかかわろうとしなかった
――ドラマや映画のほか、舞台にも頻繁に出演されていますね。2020年5月に上演される、舞台『母を逃がす』(松尾スズキ作/ノゾエ征爾演出)の主演も決定しています。「自給自足自立自発の楽園」をスローガンに掲げる架空の農業集落が舞台で、瀬戸さんが演じるのは、病に倒れた父に代わって村をまとめる頭目代行の雄介役とか。
1999年の初演と2010年の再演で、阿部サダヲさんが演じた役で、声をかけていただいて本当にありがたいなと感じています。実際に観ないとわからないのが松尾さんの作品。稽古はこれからで、僕自身もどんな舞台になるのか想像がつきません。大変そうですが、とても楽しみにしています。
阿部さんとは舞台『八犬伝』(13年)で共演し、先日、ご出演された舞台『キレイ』(19年12月)を観させていただいたときに、雄介役を演じることを報告しました。「アレをやるんだ〜。観に行くよ」とおっしゃっていましたね。すごく軽い調子でした(笑)。
――共演者の方とは、ひとつの作品が終わっても、そうやってつながっていらっしゃるんですね。
最近はそういうことも増えてきましたが、以前は違いました。芸能界に入って6年ぐらい、誰とも深くかかわろうとしなかった時期があります。最低限のコミュニケーションは取っていたので、仕事に支障をきたすことはありませんでしたが、プライベートではひとりでした。
――意外です。人とかかわることを避けていたのは、理由があったのでしょうか。
振り返ってみると、甘えだったのかなとも思うのですが…。17歳で福岡から上京してデビューしたものの、最初からたくさん仕事があるような状況ではなくて。自分の意思というよりは、親の勧めでこの世界に入ったこともあって、不安や寂しさが大きかったんですね。
初めての東京で知り合いなんていないし、周りは大人ばかりで、臆病になってしまって。何度も「帰りたい」と思いましたが、ひとり息子を東京に出した親の覚悟や、応援してくれている友人のことを思うと、弱音を吐けませんでした。誰にも相談ができず、虚勢を張ってしまって、もともとは社交的な性格だったのに、どんどん内にこもるようになっていきました。
ありがたいことに仕事をいただけるようになり、毎日はそれなりに充実していましたが、さすがに何年も続くと、「このままではダメだ」という思いはありましたね。でも、どうすればいいのかわかりませんでした。
――転機は?
『TOKYOエアポート〜東京空港管制保安部〜』(12年)というドラマがきっかけでした。ディレクターさんや照明さん、音響さんといった制作スタッフだけの飲み会に誘ってもらう機会があり、ふと参加してみたんですね。そのときに、初めてスタッフのみなさんとゆっくりと話をして、作品づくりというのは、さまざまな人たちの力で成り立っているんだなというこということをあらためて感じ、チームのひとりとしてその場にいることが心地よかったんです。それ以来、以前よりは積極的に共演者やスタッフの方々と話をするようになりました。結果的に、自分も相手も居心地のいい撮影現場からは、いい作品が生まれると実感しています。
「芝居だけど、芝居をするな」。今も頭に残る、演出家・白井晃さんの言葉

デビュー当時は壁にぶつかることも多かった。それでも続けたのは、応援してくれる家族や友人の期待に応えたいという「意地」だったと語る。「で、続けるうちに、演じることの深さを知り、楽しいなと。今では天職だと思っています」と瀬戸さん。
――ドラマや映画と、舞台の違いをどのようにとらえていらっしゃいますか?
演じるということでは大きな違いはないと思っています。ただ、『母を逃がす』もそうですが、舞台の方が非日常を演じることが多く、いろいろな可能性があるというか、映像とは異なる筋力も求められます。表現の幅が広がり、それが映像の仕事にも生きているなとも感じますね。一方で、舞台は生身の自分を試される怖さもあります。ライブという意味でもそうですが、舞台の場合、稽古のときはセットも何もないまっさらの状態から始まります。そこから、どう表現するか。最近はようやくその過程を楽しめるようにもなりましたが、自分にできるんだろうかという恐怖心とはいつも向き合っています。
――生身でぶつかる場だからこそ、周囲との関係性に助けられたと感じることは?
特別なことは思い当たらないですが、気心が知れた人がそばにいるとラクというのはありますね。例えば、『陥没』(2017年)という舞台で共演した山西惇さんはものすごく笑い上戸なんですよ。僕が何かを言うと、ものすごく笑ってくれるんです。それに助けられていましたね。雰囲気を和ませてくれる人がいると、とても安心できるというか。
――監督や演出家の方々との関係性についてもうかがいたいと思います。とくに影響を受けた方はいますか?
みなさんからそれぞれいろいろなことを教わりましたが、例えば、演出家の白井晃さん。初めてご一緒した舞台『マーキュリーファー』(15年)では、ものすごくしごかれました。稽古中に「もう帰れ!」と言われて、「帰りません。やらせてください!」と食い下がったりして、完全にスポ根の世界(笑)。でも、愛のある厳しさでした。白井さんがおっしゃった「芝居だけど、芝居をするな」という言葉が今も頭に残っています。最初はまったく意味がわからなかったのですが、段取りや台詞、役作りなどすべてをひっくるめて自分のものにしなさいという意味だと今は解釈しています。
――ダイレクトに言葉で教えられるということではないんですね。
そういう方もいますし、「こうしなさい」と教えていただいてうまくいく場合もありますが、答えはやはり、自分自身で見つけないと自分のものにはならないですよね。ときどき僕も後輩からアドバイスを求められることがありますが、最終的にはその人次第だと感じています。
仕事に対して「真面目」な人が多いと、現場の空気が心地いい

ケラリーノ・サンドロヴィッチ氏作・演出の舞台『陥没』への出演も、役者としてのひとつの転機だったと振り返る。それまでの瀬戸さんが演じたことのない風変わりなキャラクターを好演し、大きな注目を浴びた。
――デビューされて15年。後輩も増えてきましたよね。
増えましたが、慕ってくれる後輩は少ないです(笑)。それだけに、何か相談されたときは、割と真剣にアドバイスをするほうだと思います。
――相談されたときに一生懸命答えたくなる相手というのは、どんな人でしょうか。
まず、自分を信頼してくれている人。本当に僕の意見を聞こう、参考にしようと思ってくれていることが伝わると、やはり応えたいと思いますね。あとは、成長しようとしているというか、上に行こうと頑張っている人。そういう人と一緒にいると、先輩とか後輩とかは関係なく、僕自身も力をもらえます。
――最後に、瀬戸さんが一緒に仕事をしたい人の条件をひとつだけ挙げるとしたら、何でしょう?
うーん、仕事に対して真面目な人がいいです。うまく表現できないのですが、適当じゃない人。世の中には、どこか投げやりで、「この仕事を辞めても、次の仕事があるから大丈夫」というような感覚で仕事をしている人もいると思うんです。そういう人が職場にひとりでもいると、空気がよどむというか…。
それに対して、自分から望んで就いたかどうかにかかわらず、与えられた仕事に前向きに取り組む人もいる。幸い、僕の周りには後者が多いです。仕事に対して真面目な人が多いと、現場の空気が心地よく、モチベーションが上がるように思います。
Information
瀬戸さんが主演を務める舞台、シアターコクーン・オンレパートリー2020『母を逃がす』が2020年5月7日(木)から25日(月)まで東京・渋谷のBunkamuraシアターコクーンで上演される同作は2020年1月にシアターコクーンの新芸術監督に就任した松尾スズキ氏が1999年に自身の劇団・大人計画で上演した話題作(2010年再演)。今回は俳優、脚本家、演出家として活躍するノゾエ征爾氏が演出を手がける。「20年ほど前に初演されたとは思えない、今の社会を表しているような作品。それを東京2020オリンピック・パラリンピックが開催される、日本の節目となる年にどう世の中に放つか。自分の殻を破るという思いも込めて、革命を起こすような気持ちで臨みます」と瀬戸さん。東京公演チケットの一般発売は2020年3月1日(日)から。詳細はbunkamura公式サイト(http://www.bunkamura.co.jp)。
※2020年6月6日(土)〜7日(日)に新歌舞伎座で大阪公演も予定されている。詳細は大阪キョードーインフォメーション(http://www.kyodo-osaka.co.jp)。
取材・文/泉 彩子 撮影/刑部友康