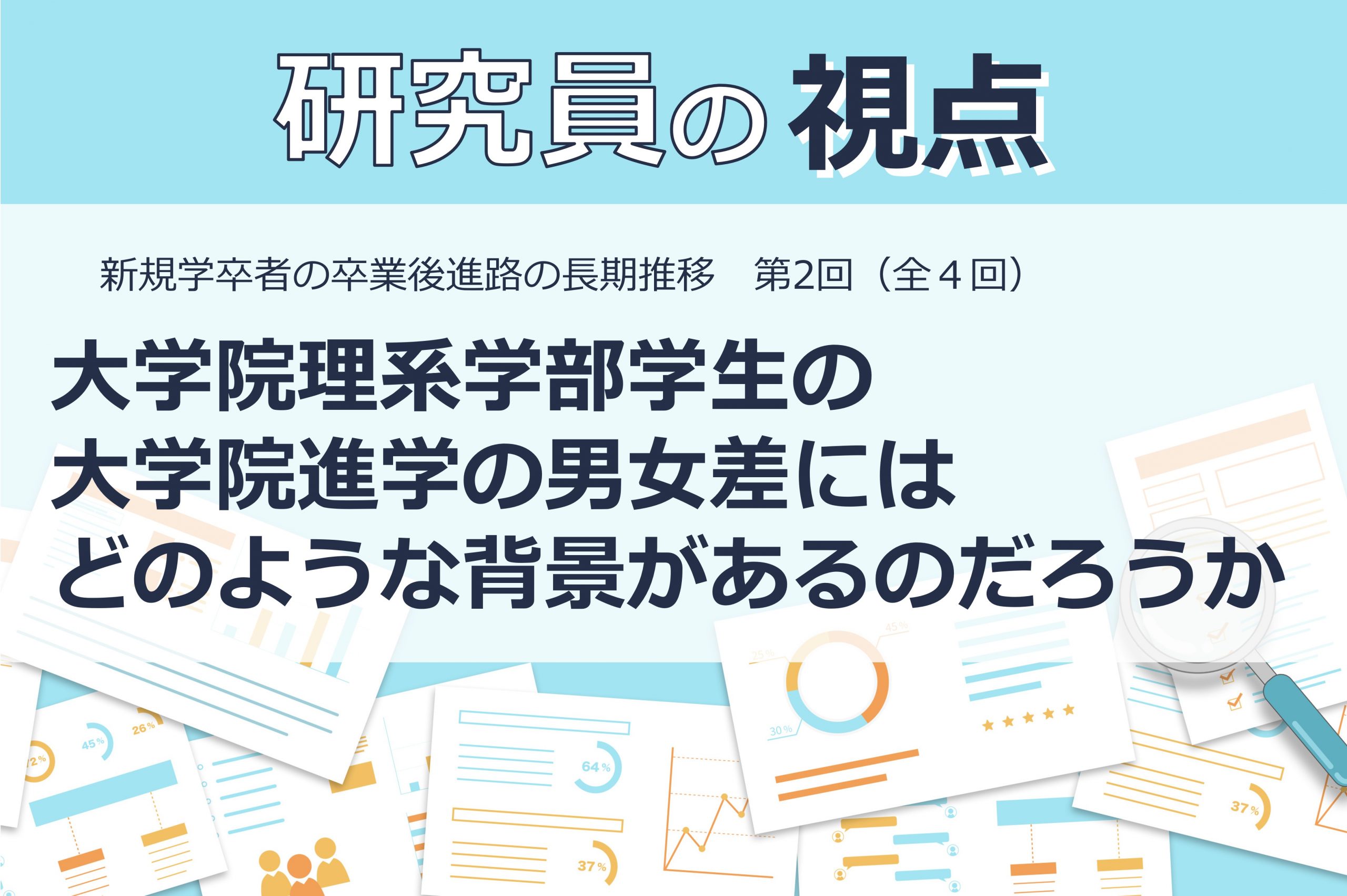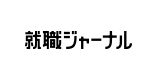【個人と組織の新たなつながり方―採用・就職活動編―】Vol.17 損害保険ジャパン株式会社
損害保険ジャパン株式会社では、2025年度入社の新卒社員の配属に際して、新卒社員向けの公募制度「新卒ジョブ・チャレンジ制度」を導入します。その背景やねらい、加えて、同社が長年設けている社内公募制度「ジョブ・チャレンジ制度」を始めとしたキャリア支援制度について、人事部の鳥越崇史さんと米山敬子さんにうかがいました。
損害保険ジャパン株式会社
人事部 企画グループ グループリーダー
鳥越崇史さん(右)
損害保険ジャパン株式会社
人事部 採用グループ グループリーダー
米山敬子さん(左)

※記事は、2024年12月6日に取材した内容で掲載しております。
【Company Profile】
1888年の創業。「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」をパーパスとして損害保険事業を展開。近年は、アプリのインストール不要でスマートフォンの操作のみでレッカー車手配と手配後のレッカー車の位置情報と到着時間をリアルタイムに把握できる「次世代ロードサービスシステム」や、宇宙保険、宇宙ビジネス支援サービスなど新たな商品・サービスの提供も開始している。
学生時代に得たスキルや経験、専門性をキャリアの入口から生かす
―御社が「新卒ジョブ・チャレンジ制度」(以下「新卒ジョブチャレ」)を導入されたのは、どのような背景からでしょうか
米山:「配属ガチャ」といった言葉が象徴するように、近年、希望する部署で働くことのできる会社を望む傾向が学生さんたちの中で強まっていることを感じています。また、私たちも面接をしていると、長期インターンシップやアルバイトなどの課外活動でスキルや経験を得ていたり、学業で専門性を培ってきたりしている学生さんに出会います。そういったスキルや経験、専門性を初期配属というキャリアの入口から生かすことができる制度を作ることで、入社後、より働きがいを感じてもらえるのではないかという考えから制度の検討を始めたという経緯があります。
―実際には、どのような流れで公募や選考を進めていらっしゃるのでしょうか
米山:まず、2024年10月の内定式で制度を発表し、11月に詳細についての説明会をオンラインで実施しました。説明会では、制度のねらいと、募集ポストがどれだけあるかを説明した上で、募集ポストに従事している社員からそれぞれの部署の特徴や業務内容などについて説明してもらう時間を設けました。
そして、12月締切で応募を受け付け、エントリーシートと適性検査、面接を経て最終的な合格者を決定する予定です。合否については、入社後2カ月間の研修期間中に全新入社員を対象に行う配属発表で分かる形にします。合格していれば応募した部署に配属されていますし、そうでなければ別の部署に配属されていることになります。
なお、新卒ジョブチャレへの応募の有無にかかわらず、内定者全員に対して毎年、勤務地や配属部署の希望調査を行っています。応募のない人についてはその希望を元に配属を検討します。
―この制度の発表以後、内定者の皆さんからはどのような反響がありましたか
米山:10月の内定式で伝えた際には「興味ある」「チャレンジしてみようかな」といった声が割と多く聞かれました。ただ、実際に募集してみると、躊躇している様子も見られるため、応募が殺到するような状況にはならないと予測しています。
―次の2026年卒業予定の学生の採用活動においては、学生がすでにこの制度を認知しています。どのようにコミュニケーションをとっていかれる予定ですか?
米山:2025年卒の採用活動の時点ではまだ公表していなかったためPRできませんでしたが、2026年卒採用においては会社の制度としてきちんと説明してきたいと思っています。そうすると、「2025年入社の人たちからはどのくらい応募があり、どれだけの人が希望部署に配属されたのか?」などの質問も受けるでしょうから、伝えられることは伝えていきたいと思っています。
他方で、初期配属で希望する部署にチャレンジすることだけが全てではなく、キャリアの中でいつ、どのような制度や仕組みを活用するかは人それぞれで、正解も不正解もないということもちゃんと伝えておきたいと思っています。
―今後の計画として、この仕組みを採用選考の段階から取り入れる予定はありますか
米山:まだ検討中です。すでに一部の職種では、採用選考の時点でコースを設けて選考を行っていますが、それは「アクチュアリー」「データサイエンス」「IT・システム」「資産運用」「法務」「経理・財務」という特定部門での専門性が求められる職種のみです。営業部門や保険金サービス部門といった多くの新入社員が配属される部門・職種についてコースを設定して募集することにはまだ踏み切っていません。
というのは、内定後や入社後にさまざまな社員や仕事に出会うことで、望むキャリアや配属の希望は変化していくことがあるからです。にもかかわらず、選考会のエントリー時点で、例えば営業のコースや保険金サービスのコースを設けると、それ以外への配属という選択肢がなくなってしまいます。これらについては、あえてコースを限定しなくてもいいのかなと思っています。
社内公募制度を時流に合わせて更新し、社員のキャリア形成を支援
―御社は、社内公募制度「ジョブ・チャレンジ制度」も設けていらっしゃいます。この制度の概要やねらいについても教えてください
鳥越:ジョブ・チャレンジ制度は20年以上前からある制度です。社内公募制度は今でこそ様々な企業で実施されていて、社員のリテンションのための強い武器になっている側面がありますが、当社においては、当時はシンプルに社員のキャリア形成やスキルアップなどの観点で作られたと認識しています。
そこから、地域限定で採用された社員のキャリアの選択肢を増やし、知見を広げてもらいたいといった人材育成の意向や、コロナ禍でのリモートワークの浸透など、その時々の時流に合わせて制度の中で様々なコースを新設したり改良を加えたりして、現在のコース設計になっています。
―現在はどのようなコースがあるのでしょうか
米山:希望の部署に応募できる「チャレンジコース」、居住地を変更することなくフルリモートで他地域も含めた他部署に勤務する「リモートチャレンジコース」、リモートチャレンジコースほど長期間ではなく、1年間限定でフルリモートで他地域も含めた他部署に勤務する「ジョブトライコース」、半年間ほど他部署の業務を経験する「インターンコース」、定年後の再雇用社員向けの公募「エルダーコース」など6つのコースを設けています。
―2023年度は155名の方がジョブ・チャレンジ制度に合格されています。5年間で合格者が倍増していますが、増加傾向にあるコースなどはあるのでしょうか
米山:特定のコースが激増しているということはなく、全体で増えています。また、コースごとの応募状況を見ると、応募・合格が圧倒的に多いのはチャレンジコースです。他方で、例えばリモートチャレンジコースは、2021年の新設時は合格者が数名ほどだったのが今では十数名に増えるなど、チャレンジコース以外のコースもだんだんと社員に浸透してきている状況です。
―今後も、状況に応じてコースを新設したり変更したりすることも考えていらっしゃいますか
米山:そうですね。現状でもたくさんの社員が応募している一方で、「応募しよう」と思えない社員ももちろんいますから、自律的にキャリアを形成していく第一歩を踏み出すための機会として、踏み出せない人のネックになっていることは取り除いていければと思っています。ちなみに、リモートチャレンジ制度などはまさに「体ごと異動・転勤するのは無理だ」というネックに対するアンサーとして設けた制度です。
また、ジョブ・チャレンジ制度ではありませんが、2021年に新設した社内副業制度「SOMPOクエスト」もネックを取り除く制度の一つと言えます。
―どのような制度でしょうか
米山:所属部署の業務を行いながら、所定の就業時間の2割を上限に他部署の業務に携わることができる制度です。全国の部署が業務単位で募集し、参加を希望する社員が自ら応募できる仕組みとしています。部署異動というチャレンジまではせずに、他部署がどのようなことを考えてその業務に取り組んでいるのか知りたい、自分のスキルを他部署でも活かしたいといった社員が使い始めています。
現部署での挑戦と他部署への挑戦、どちらもできる環境を整備していく
―今日のお話から、社員の皆さんがキャリアを築いていく上で多様な選択肢を設けていらっしゃることがわかりました。改めて、どのようなお考えからこれらの施策に取り組んでいらっしゃるのでしょうか
鳥越:個人が自律的にキャリアを形成していく重要性は以前から世の中で言われていて、当社でもその考えを取り入れて20年くらいになります。ただ、なかなかゴールに辿り着けていないため、ゴールに向かうには選択肢を増やしていくことと、自ら手を挙げられる環境を作っていくことが重要だという考えで様々な制度を作っています。ここはこれからも継続していくところです。
他方で、目の前の仕事が楽しく感じられない状況になるのはあまり健全ではないという思いもあります。例えば、先ほど紹介した社内副業制度の場合、自分の成長のために副業を始める人もいれば、隣の芝が青く見えて逃避的にのぞきに行きたくなってしまう人もいると思っています。本業が楽しく感じられない会社というのはすごく残念なので、ちゃんと本業にフォーカスを当てられるよう、人事部として人事やキャリアの戦略を練っていきたいと思います。
具体的には、「今いる部署で積極的に活躍したい」「所属部署で成長していきたい」といったことを宣言できる環境を作ることも大事でしょうし、他部署にチャレンジしたいと思った時に選択肢があることも大事です。この両面ともをしっかりとやっていきたいと思っています。
―では最後に改めて、今後の採用活動や人事施策において目指したいことや取り組んでいきたいことなどについて教えてください
鳥越:目指すところは、「社員の働きがいの実現」の一言に尽きます。そのために、人事戦略や施策を作る際には「どうすれば働きがいに繋がるのか?」ということを常に意識して取り組んでいきます。
米山:入社という入口で、自分にマッチした会社・配属であるという実感を持って入社していただくことがその後の会社人生を楽しめることに繋がっていくと思うので、当社の魅力をきちんと伝えていけるよう採用活動に取り組んでいきたいと思っています。
取材/中村洋和 文/浅田夕香 撮影/刑部友康