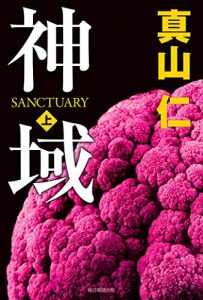さまざまな分野で活躍する有名人の方々を直撃インタビュー。
もしも今の仕事をしていなかったら、どんな職業を選んでいたかを想像していただきました。どんなお話が飛び出すでしょうか。
Vol.6 小説家 真山 仁さん
2018年夏に2度目のドラマ化で話題を呼んだ『ハゲタカ』の著者として知られる真山 仁さん。日本経済の問題点を鋭く描いた『ハゲタカ』シリーズをはじめ、震災後の原発政策とリーダーシップのあり方を問う『コラプティオ』、日本の食の安全と農業をテーマにした『黙示』など現代社会の抱える問題に真正面から向き合いつつ、エンターテインメント性の高い小説を世に出し続けています。
高校生のころから「小説家になる」と決めていたと言う真山さんですが、もしも小説家になっていなかったら、やっていたと思う仕事があるそうです。その仕事とは…。

まやま・じん●1962年、大阪府生まれ。87年、同志社大学法学部政治学科卒業後、新聞記者として中部読売新聞(現・読売新聞中部支社)に入社。89年、同社を退社。フリーライターを経て2004年、熾烈な企業買収の世界を赤裸々に描いた『ハゲタカ』でデビュー。『ハガタカ』『ハゲタカⅡ(「バイアウト」改題)』は、NHK土曜ドラマになった後、18年にテレビ朝日系で連続ドラマ化。また、『レッドゾーン』も09年に映画化されている。シリーズ最新作は、原発事故に見舞われた電力会社の買収劇を描いた『シンドローム』。そのほかの著書に日本の食と農業の問題に斬り込んだ『黙示』、地熱発電をテーマにした『マグマ』、中国での原発建設を描いた『ベイジン』など。
――小説家になっていなかったとしたら、どんなお仕事をしていたと思いますか?
再び新聞記者をやっていたと思います。
――真山さんは大学を卒業して新聞記者になり、2年半で退職されていますよね。一度お辞めになった仕事をなぜ?
新聞記者という職業に、自分が負けたからです。もともと新聞記者の仕事は小説家になるためのステップと考えていましたが、入社時には10年続けるつもりでした。辞めたのは、会社と自分の考えにズレがあり、「読者に本当に伝えたい記事を書けない」と感じたから。2年半とはいえ全力で仕事に取り組み、当時の自分としてはやるだけのことはやったつもりです。だから、後悔はありませんが、反省はしています。新聞記者を辞めて30年近くたった今、はっきりとわかるのは、当時の自分が書きたい記事を書けなかったのは、会社のせいでも、上司のせいでもない。私の能力が足りなかったからです。
――どんな力が足りなかったのでしょう?
一番大きいのは、「このチャンスを絶対に生かしてやる」という気迫だと思います。新聞記者時代の同期たちと今もときどき会うのですが、局長や部長になった彼らから、「若い記者に取材の仕方を教えてくれ」と言われることがあります。「長年記者をやってきたお前たちが教えるのが一番じゃないか」と答えると、「そうじゃないんだ」と。名刺を持たない人間がどんな取材をしているのかを知りたいと言うんです。
確かに私には、大企業の社員が持っているような名刺はありません。『ハゲタカ』で少し名前を覚えてもらったとはいえ、「真山仁? 誰、それ」という人が大多数です。そんな状況のもとで、刑事や検察官、大企業の経営者といった方たちにアポイントを取り1、2時間ほどで取材する。初めて会った人と限られた時間で関係性を築き、彼らが自分からは語りたがらない重要な情報をなぜ引き出せるのか。新聞記者からは不思議がられますが、私から言わせれば、当然のことです。
名刺ひとつであらゆる人に取材できる新聞記者と異なり、私たちフリーランスに取材のチャンスは滅多にめぐってきません。取材をする人がこれからも協力者になってくれるか、今日で「さようなら」なのかは、初対面での取材時が勝負です。だから、一回一回の取材に「どうしてもこの人をブレインにしたい」「この人からこの話を聞きたい」という気迫で臨むことになる。すると、取材相手とのコミュニケーションの取り方から質問の切り口まで自ずと変わってきます。
再び新聞社に入り、今度は“名刺を持たない取材”を続けたら、かつてやり残したことをどこまでできるのかを試してみたいという思いがあります。ただ、「小説家になっていなかったら、新聞記者に」と考える理由はそれだけではなくて、最近、新聞記者にエールを送りたいという気持ちが強くなっているんです。
――エールとは?
「新聞記者という職業に誇りを持て」「自らが読者に伝えるべきだと思う記事を書くことから、逃げるな」と言いたいのです。小説家として取材を受けたり、取材の協力をいただいたり、いろいろな新聞記者の方に会う機会があって、一人ひとりはすごく優秀だと感じています。ただ、ひとつ気になるのは、戦う前から負けている人がすごく多い。今は空気を読むことを求められ過ぎる時代で、メディアまでもが権力者や世論を気にして自主規制する傾向があるので、「うちの会社でこれを書いても、どうせ記事にはならない」とあきらめてしまっている記者がたくさんいるように見受けられます。
小説家と違って、新聞記者には大きな舞台が最初から用意されています。新聞購読者は昔に比べて減っているとはいえ、1000万人を超える人たちが毎日どこかの新聞を読んでいます。一冊一冊を買ってもらってようやく読んでもらえる小説と比べると、自分が書いたものを誰かが読んでくれる確率ははるかに高い。つまり、自分が疑問に思ったことを「あなたはどう思いますか?」と世に問うチャンスをふんだんに与えられているんです。
おまけに、新聞記者は多くの「特権」を持っています。取材のためなら一般の人が入れない場所に入れ、極端な話をすれば、一方通行の道の逆走すら認められることさえある。なぜそんな「特権」を与えられているかと言うと、新聞記者の持つ訴求力、「ペンの力」にみんなが期待しているからです。わかりやすい例を挙げると、記者クラブに所属していれば、安倍総理大臣に政治の疑問を直接投げかけることもできる。それだけの責任がありながら、なぜ通り一遍の質問しかしないのか。2年半で新聞記者を辞めた私が何かを言える立場ではありませんが、新聞記者がものすごく大事なものをなくしつつあることが歯がゆいのです。
同じ「取材をしてものを書く仕事」であっても、新聞記者と小説家ではそれぞれの立場だからこそできることがあります。組織の力を使って、地道に何人もの人が取材をして多角的な視点から現実をとらえながら書くということは、小説においては難しいでしょう。そして、小説は現実に勝てません。「事実は小説より奇なり」という言葉がありますが、その通りで、小説では「こんなシーン、あり得ない。嘘っぽいから書き直してください」と編集者から必ず言われるようなことが現実には起きる。そんな「あり得ない」現実の問題に光を当て、世に問うことは新聞記者にしかできません。
私は小説家ですから、小説だからこそできる表現を追求し、自分の問題意識を世に問い続けていきます。だけど、もしも小説家でなかったら、もう一度新聞記者になって、逃げずに伝えるべきことを伝えたい。結局、私がやれること、やりたいことというのは「取材をしてものを書く仕事」しかないみたいです。
<「お悩み」相談コーナー>
アンケート回答者から寄せられた「お悩み」に真山 仁さんからコメントをいただきました。
<真山さんチョイスの「お悩み」>
早い時期に内定をもらって就職活動を終えましたが、本当にそこで良かったのか不安が残っています。入社予定の企業について妥協した点もいくつかあるので、探せば、もっといい企業があったのではと思ったりしています。
(就職プロセス調査 8月調査回答・大学生・理系・女性)

まず、考えてみた方がいいと思うのは…。

あなたの「いい企業」の基準は何ですかということです。入社後に「こんなはずじゃなかった」と思い知るような不幸な就職になりやすいのは、「取りあえず名のある会社に入ろう」と「人気企業ランキング」を基準に就職先を選ぶこと。ただ、その場合は、入社前に悩んだりはしないと思います。内定をもらえたのがランキング5位と25位、70位の企業だとして、より上位の企業に入社すればいいだけのことですから。
悩むのは基準がはっきりしていないからです。はっきりさせるには、どの企業に入りたいかではなく、何をしたいかを考えること。例えば、チョコレートが大好きで、「おいしくて、安全なチョコレートが作りたい」と考える人がある程度の規模で名の知れたお菓子メーカーと、小規模で創業間もないお菓子メーカーに内定をもらったとします。組織が大きな企業は利潤重視になりがちだから、おいしさや安全を本当に追求するのは難しい可能性もある。一方、後者は若手も自由に仕事ができそうで、会社の理念と自分の考えも合っているけれど、企業として安定はしていない。その時に「自分が何をしたいのか」を基準に選択すれば、いくつか妥協点があったとしても、入社後に後悔する確率は少なくなるはずです。
入社前に「内定をもらったけれど、本当にそこで良かったのか不安」という人の多くは、「マリッジブルー」にかかっているようなものかもしれません。
――結婚を前に「本当に彼(彼女)で良かったのか」と考えてしまうアレですね。
はい。「隣の芝生は青い」と言いますが、比べればキリがない。別の会社を探して内定をもらっても、「自分の基準で選んだ」という確かな思いがない限り、同じことの繰り返しになるでしょう。「マリッジブルー」の解消法は、ふたりの生活を始めてみるしかない。就職も同じで、妥協点ばかりを気にして「やっぱり、失敗だった」と思っていては幸せを逃します。「成功なんだ」と信じて新しい生活に踏み出す準備をしましょう。
Information
真山さん初の医療サスペンス『神域』(毎日新聞出版/上・下巻 各定価:1500円+税)。脳細胞を蘇らせる人工万能幹細胞「フェニックス7」それは人間の尊厳を守るために生み出されたはずだった。国家戦略の柱としたい日本政府は一刻も早い実用化を迫る。再生細胞による医療が普及すれば、人は永遠の命を手に入れるかも知れない―。しかし、本当に細胞は安全なのだろうか。
※本文は2018年取材時の内容で掲載しております
取材・文/泉 彩子 撮影/刑部友康