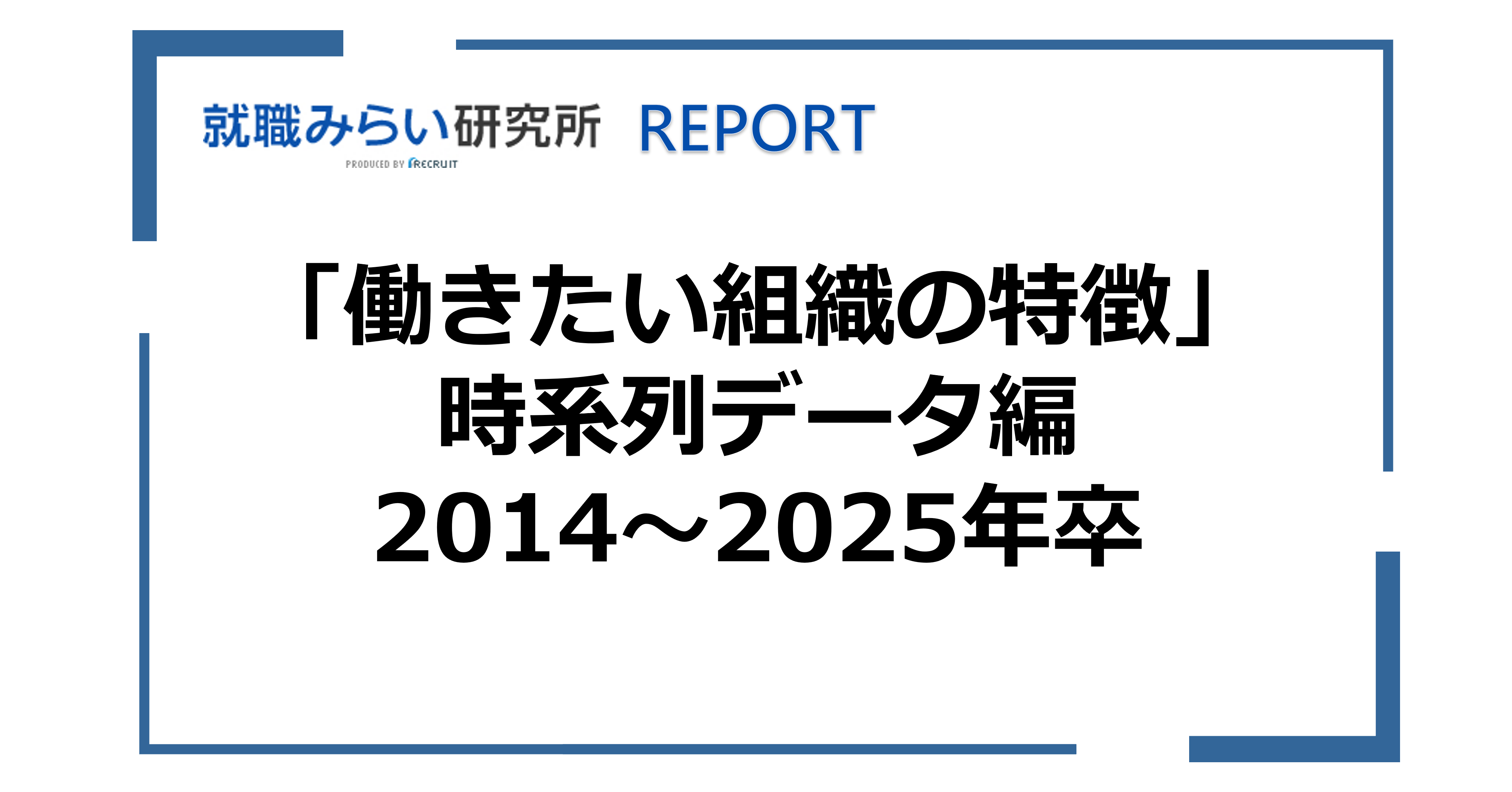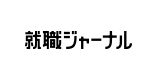【個人と組織の新たなつながり方】Vol.13 琉球大学
琉球大学では、沖縄県内企業と連携したインターンシッププログラム「うりずんインターンシップ」を2014年から運営するほか、経済団体と連携した県外での就業体験や、沖縄県内自治体での就業体験等、さまざまな就業体験の機会を提供しています。低学年学生への就業体験支援にも積極的です。琉球大学で学生のキャリア教育・キャリア支援を行う武田和久さん、屋嘉部一美さんにお話を伺いました。

※記事は、2024年12月12日に取材した内容で掲載しております。
【グローバル教育支援機構 准教授 武田和久さん(左)】
大学卒業後、メーカー・保険の営業職を経て独立。独立後はマネジメント、リーダーシップ、モチベーションなど管理職・リーダー職を対象にした研修・講演活動を行う。2023年より現職。
【キャリア教育センター 特命一般職員 屋嘉部一美さん(右)】
大学卒業後、営業職等を経て専門学校講師を機に学生のキャリア支援に携わる。2021年より初年度対応型インターンシップ事業等を担当。国家検定2級キャリアコンサルティング技能士。CIAC認定インターンシップコーディネーター。
【国立大学法人琉球大学 グローバル教育支援機構 キャリア教育センター】
学生が「キャリア」について理解を深め、満足度の高い進路決定ができるよう、「キャリア形成入門」を共通教育・キャリア関連科目に導入。キャリア形成の専任教員と学生就職支援担当者が連携し、沖縄型インターンシッププロジェクト「うりずんインターンシップ」を運営している
琉球大学のキャリア教育・就業体験支援
―琉球大学は低学年生へのキャリア教育や就業体験支援を積極的に行っていると感じます。具体的にどのようなことを行っているのでしょうか。
武田:全学共通科目での授業と、事前準備・事後研修を含めた就業体験機会の提供です。授業としては、全学年が履修できる「キャリア形成入門」をはじめとした授業を開講しています。また、就業体験を伴う「キャリア関係特別講義」の授業を、専任教員とキャリア教育センターが連携して実施しています。授業を私が担当し、「うりずんインターンシップ(後述)」参画企業の募集と学生のマッチングを屋嘉部さんが中心に担当しています。
屋嘉部:本学が学生に提供している就業体験の機会は3つあります。1つ目は、本学が県内企業や団体と連携して実施している「うりずんインターンシップ」です。2014年の開始以来、100社以上の企業で1800名以上の学生が就業体験をしています。2つ目は、(一社)経済同友会インターンシップ推進協会が実施する「経済同友会インターンシップ(※1)」です。本学も正会員大学として参画しており、県外の大企業での就業体験の機会になります。3つ目に、沖縄県内自治体での就業体験の機会があります。
自分のキャリア形成に「目的」を意識してもらうための投げかけ
―授業の内容について教えてください。
武田:講義形式の「キャリア形成入門」は年間1000人ほどの学生が受講しますが、なんとなく科目選択した1・2年生も多いです。そのような学生にも、どんな仕事、働き方、生き方をしたいかを、自分ごととして考えてもらえるようにしています。学生には「何のために?」という問いを投げかけ続け、いい意味でのプレッシャーを与えています。
―具体的にどのような問いが投げかけられるのでしょうか。
武田:学生全員に毎週、1週間の行動を記録してもらい、自己評価を添えて提出してもらいます。日々のさまざまな行動がキャリアに関係しています。本を読んだでも、動画を視聴したでもいいのです。行動を振り返る体験をしてもらっています。
授業では「今日のテーマ、どう思いますか?」「今日の授業を聞いて考え方に変化はありましたか?」のように、毎回のテーマをどう受け止めたかを聞いています。考えが変わらなかったなら、変わらなかった理由を考えてもらいます。すると「私はそうは思わない」のように、自分ごととして考えて意見を発する学生が出てきます。受講者全員が自分ごとになるのは難しいですが、学生にとって周りの友人の影響は大きいです。周囲の学生にも友達が自分のキャリアについて考えている様子が伝わり、刺激を与えてくれます。
―学生一人ひとりが自分自身の「目的」を考えるための投げかけなのですね。
武田:そうです。授業では目標と目的は違うという話をよくします。例えば単位を取るのは「目標」です。その単位は何のために取るかという「目的」まで考えてもらいたいのです。キャリア形成も同じで、就職は目標に過ぎません。それを通して自分がどうなりたいか、どんな人生を歩みたいかを考えるのが肝心です。考えたことを実際に体験し、自己内省する機会として、ぜひ就業体験もしてもらいたいと考えています。
授業中もキャリア教育センターに就業体験相談をするように勧めるのですが、自分が相談していいのか戸惑う低学年学生は多いです。そういう学生には、1年生で就業体験をした人の話をすると、自分ごととして行動に移せる学生も出てきます。
屋嘉部:低学年から就業体験の相談に来る学生は、学生全体からすれば多くないのですが、授業で働きかけていただくようになってから、「武田先生に言われて」と訪ねて来るようになりました。以前の1割程度増えています。
「2社以上参加OK」の就業体験プログラム
―琉球大学が主催する「うりずんインターンシップ」についても詳しく教えてください。
屋嘉部:うりずんインターンシップは、本学が県内の企業や他大学と連携して実施する、全学年対象の就業体験プログラムです。参画する各社には、5日以上の就業体験を伴う「インターンシップ(タイプ3 ※2)」、または、数日間の「キャリア教育(タイプ2 ※2)」に該当する日程・内容を組んで、学生を受け入れていただいています。低学年学生から参加できるので、民間企業就職、公務員、進学など、自分の進路の軸を早めに検討するきっかけになります。
学生には「2社以上参加OK」と明記して参加募集をしています。同業界で2社比較したり、異なる業界で2社比較したりして、企業研究を深めてもらいたいと考えているためです。3社、4社と参加する学生もいますが、自分で参加する機会ならば主体性を持って取り組んでくれると考えています。また、うりずんインターンシップは県内の民間企業での就業体験機会になりますが、「経済同友会インターンシップ」や県内自治体での就業体験等の機会も併用して、県内企業と県外企業の比較、民間企業と公務員の比較をする学生もいます。
武田:キャリア関係特別講義の単位付与には「実習日数5日以上」という条件がありますが、複数社の就業体験の日数を組み合わせることも認めています。低学年生の場合は、A社の就業体験を2日、B社の就業体験を3日行って、合計5日間の就業体験をする学生もいますし、5日を超えて就業体験をする学生もいます。学業とのバランスや参加目的を確認しながら、指導・サポートしています。

琉球大学では教員とキャリアセンター職員が連携しながら、学生の就業体験を支援している。
目的意識を持って就業体験に臨んでもらう
―学生が就業体験をするうえで、大学はどのような支援をしているのでしょうか。
武田:うりずんインターンシップに参加する学生には、事前・事後の研修を受けてもらいます。事前研修では、自分で企業情報を収集し、分かったこと・分からなかったことを整理してもらいます。情報収集だけでは分からない部分が出てくると、就業体験中に質問しよう、という動きにつながります。学生から企業に関わりを求めていくようになります。
屋嘉部:学生が主体的に就業体験に臨むようになることが、事前研修の価値です。企業は日常業務と並行して学生を現場に受け入れます。学生には、就業体験の機会を得られることが当たり前だと思わず、企業の受け入れ準備への感謝の気持ちを持って臨む姿勢が大事だと伝えています。うりずんインターンシップと同時期に、自由参加する学生も受け入れている企業には、「(うりずんインターンシップを通して参加する学生の方が)積極的に質問し、意欲的に参加している」と言われることもあります。
武田:企業への感謝の気持ちを持つことは、本学の学長が学生に向けて伝えている言葉でもあります。そして学生が就業体験に臨むうえでは、目的意識が重要です。受け身の姿勢で就業体験に参加すると、多くの社員の方々と接する機会を得た結果、「なんとなく参加して良かった」という感想にとどまる場合があります。一方で、目的を持って臨むことで、就業体験を通じて得られた経験や企業への理解が深まったかどうかを具体的に振り返ることができるようになります。

事前研修では、「目的」と「目標」の違いを改めて認識しながら、学生主体で企業の情報収集や就業体験で確認したいことの整理をする。
―事後研修の内容も教えてください。
屋嘉部:事後研修では参加者全員にA0判の成果発表ポスターを作成してもらい、企業も参加する成果発表会の場でポスター発表してもらいます。経済同友会インターンシップで教わった考え方でもありますが、「“経験に学ぶ”のではなく、“経験を振り返ることに学ぶ”」という点を意識して、学びや気付きを言語化してもらっているので、ポスターの内容も濃くなります。このポスターデータは参画企業各社へのフィードバックとしても提供しています。
武田:ポスター発表は100人近くの学生が発表しますが、事務局が全員のポスター作成をフォローしています。学生から試作版のポスターが提出された後、就業体験中の日報や企業のフィードバックシートを読み込んだうえでアドバイスコメントが返されています。そのうえで学生から完成版ポスターが提出されます。事務局の学生一人ひとりへのサポートは、とても手厚いと感じています。
屋嘉部:受け入れてもらった企業での就業体験の報告なので、就業体験を通して見つけた企業の魅力を表現するようにアドバイスしています。
企業に依頼していることもあります。複数の学生を受け入れた場合も、「学生さんたち(全員)」ではなくて、参加者一人ひとりにフィードバックしていただくようにお願いしています。丁寧に返してくださる企業からは、学生をわが子のように見守っていただいたことが伝わってきますし、いい関係になっていると感じます。成果発表では、他社の実習の様子も分かるので、リサーチを兼ねて見学にいらっしゃる方も増えています。
武田:あくまでも仕事は手段で、仕事を通して自分がどうなりたいかを考えないと、就職がゴールになってしまいます。学生が目的意識を持って就業体験をすると、学生自身が主体的にキャリアを選択できるようになっていくのではないでしょうか。
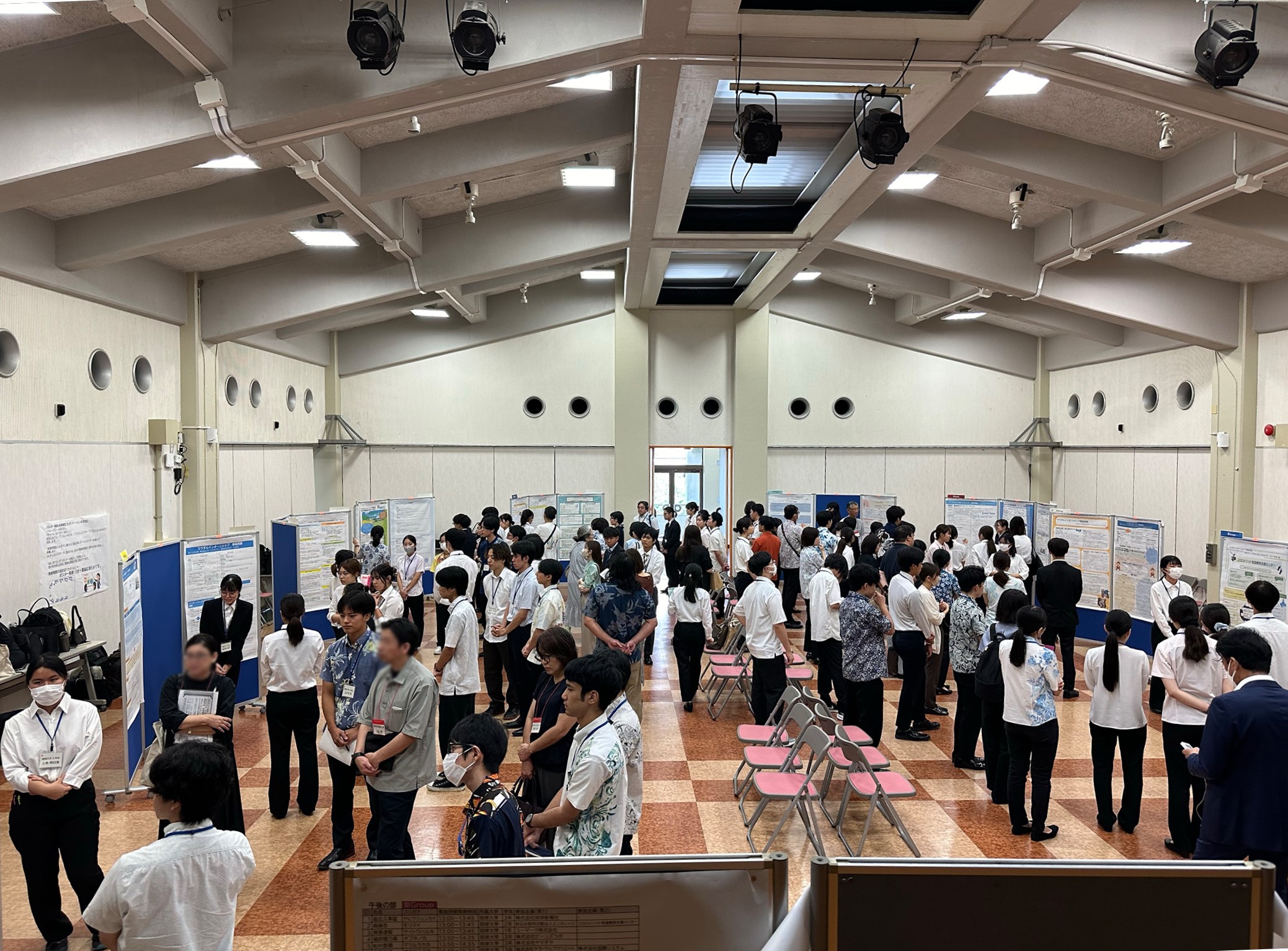
事後研修では就業体験に参加した学生一人ひとりが、参加企業の概要や就業体験を通して得た気づきをA0判ポスターにまとめ、他の参加学生や参画企業各社に向けて発表する。
嵩元 盛翔さん
人文社会学部 国際法政学科 法学プログラム 2年生
将来の軸になる仕事を見つけようと、1年生の後半からキャリアに関する授業やセミナー等に参加しました。武田先生と面談で「うりずんインターンシップ」や「経済同友会インターンシップ」を案内いただき、県内・県外各1社の就業体験に参加しました。業種は2社ともIT業界を選択。学外のオンライン講座でもプログラミングを学んでおり、IT業界の仕事・業界を体験したいと考えていました。
県外での就業体験は東京の企業です。東京で生活するイメージを持てました。一方、就業体験をした企業はインターネットインフラの会社で、自分がITエンジニアとして描いていた業務内容やキャリアプランとは異なりました。自分としては経験を積みたいという志向があることを整理できました。県内企業でも就業体験をしましたが、フロントエンジニアとして県内企業に就職した場合、最初は東京などで研修を受ける企業が多いことも分かりました。就業体験を通して、自分はまずは県外に就職してスキルを磨き、将来的に地元に貢献できるようになりたいと思うようになりました。
就業体験をして、自分で体験することが進路を選ぶ納得感につながると分かったので、来年の夏はインターンシップに参加して、自分に合った仕事や環境を探していきたいです。
辺士名 洸さん
人文社会学部 琉球アジア文化学科 文学プログラム 2年生
1年生の後期に友人と、武田先生の「キャリア形成入門」を受講しました。先生は教室を歩き回りながら、問いを立てては学生同士で話し合わせ、発表させます。初めは緊張しましたが発見も多く、キャリアについての考えが変わっていきました。親族と同じ高校教師を志望していましたが、それ以外の選択肢も見てみようと思うようになりました。
「うりずんインターンシップ」で就業体験をしたのは、テレビ局スタッフ、物流企業のマーケティング職、観光施設のスタッフ、電気設備商社の営業職の4社です。自分の興味のほか、沖縄で仕事をする機会が多そうな業界・職種を選びました。それぞれの仕事に発見があったなか、特にマーケティングの仕事の幅広さを感じました。就業体験をしたのは沖縄県内に複数のグループを持つ企業でした。沖縄の物流を支えるという、目立ちにくいけれどスケールの大きい仕事を体験できました。基本的には県内で仕事をしていくことを考えていますが。、県外のOB・OGインタビュープログラムにも参加予定なので、今後は県外就職の選択肢も比較したいと思っています。就業体験は大学での勉強にも影響していて、今後は地域公共政策士(※3)という地域活性化に関連する資格が取得できる科目を選択したいと思っています。
文/衣笠 可奈子 撮影/難波 卓美(CURBON)
※1 一般社団法人経済同友会インターンシップ推進協会が運営する、学部1・2年生、高専本科4年生・専攻科1年生を対象とした就業体験。
https://www.doyukai-internship.or.jp/internship/
※2 2022年6月に改正された、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)で整理された学生のキャリア形成支援の取り組み4類型。下記4タイプに整理された。
タイプ1:オープンカンパニー(単日・全学年対象・就業体験無しの企業等によるイベントへの参加)、
タイプ2:キャリア教育(日数規定なし・全学年対象・就業体験任意の大学主導型の産学共同プログラム)、
タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ(5日以上・学部3年以上学生もしくは修士学生対象・就業体験必須の企業主導もしくは産学連携のプログラム)、
タイプ4:高度専門型インターンシップ(長期・修士もしくは博士学生対象・就業体験必須のプログラム)
【参考】
・文部科学省・厚生労働省・経済産業省(2022)「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(令和4年6月13日一部改正)」https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/20220610-mxt_ope01_01.pdf
・就職みらい研究所(2024)『就職白書2024』p16,「2025年卒向けキャリア形成支援プログラムの実施状況」
https://shushokumirai.recruit.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/hakusho2024_0424_16-17.pdf
※3 一般財団法人地域公共人材開発機構が地域で活躍する公共人材の能力を認定する資格。