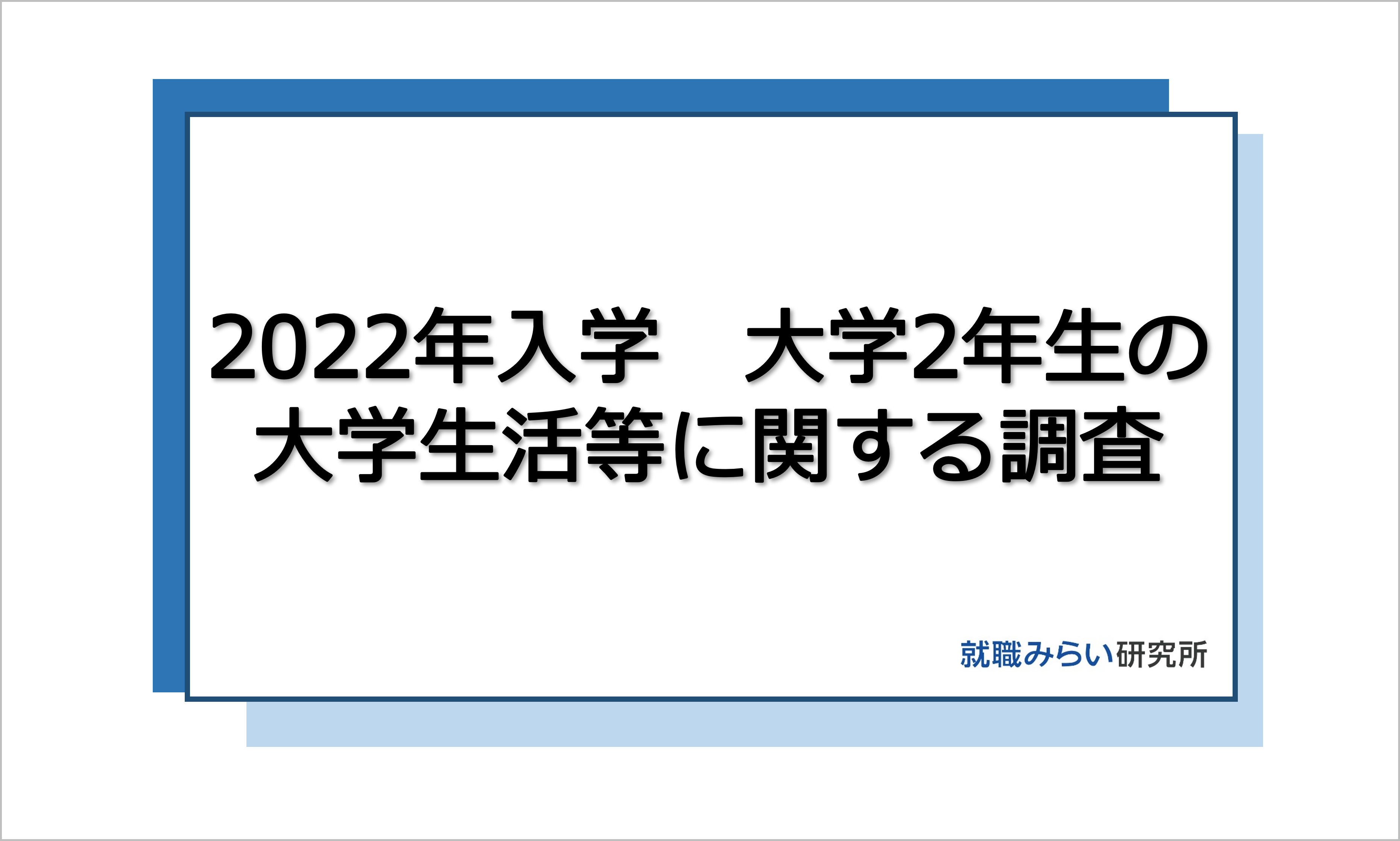各界の著名人に、これまでに出会った、プロとしてすごいと思った人、影響を受けた人など「こんな人と一緒に働きたい!」と思う人物像をインタビュー。
一緒に働いていて心地いい人の大前提は、「明るい人」

たかはし・まあさ●1981年、東京都生まれ。2004年、株式会社フジテレビジョン入社。13年退社後、フリーアナウンサーに。抜群の歌唱力と明るいキャラクターでテレビ、ラジオ、イベントで活躍中。日本テレビ『スッキリ!!』、フジテレビ『バイキング』、テレビ東京『ソレダメ!』などのレギュラー番組を持つ。趣味は歌を唄う、料理、ゴルフ、演劇鑑賞。
「明るい人」というのは、人との距離感を上手に測れる人
――真麻さんが一緒に働きたいなと感じる人の第一条件は?
「やる気がある人」とか「その仕事が好きな人」もいいなと思いますが、私自身が仕事をしていて一番やりやすいのは、「かゆいところに手が届く人」。そういう方たちというのは、ちゃんと周りを見ていて、相手との距離感の測り方が上手なんですね。だからこそ、相手が求めているものや、その現場で、今、取るべき対応というのがわかる。それができるということは、その人のキャリアの積み重ね方や、本来持っている素質、常に周囲に目を配れる人かどうかといったことを示していると思います。ただ、大前提としては、やっぱり明るい人がいいです。
――やっぱり、そうですか。
はい。でも、この明るさも、正直、ただ明るいだけでは、「ちょっと、めんどくさいな」とか、少し押しつけがましいなと感じることがありますよね。そう考えると、相手にちょうどよく「明るい人だな」と感じさせる人というのも、距離感の測り方が上手な人なんだと思います。なかなかそんな完璧な人なんていないんですけどね(笑)。
――真麻さんご自身も、仕事をするうえで人との距離感は大事にしていますか?
そうですね。とくに、番組でアシスタントMCを務めさせていただくときは、一緒にお仕事をするメインMCの方との距離感をとても大事にしています。アシスタントを務めるときの私の信条は、メインMCの方への愛情とときめきを忘れないこと。メインMCの方が番組を進行しやすいよういかにサポートするかを考えて、間合いや呼吸を探りながらやっています。
そのときに、適正な距離感というのは相手の方の性格や、その日のコンディションにもよります。例えば、カメラが回っていないところで他愛もない話をすると距離感が縮まるタイプの方もいらっしゃれば、ちょっと距離を置いて程よい緊張感を保った方が本番でスイッチが入ってうまく運ぶ方もいらっしゃる。ですから、相手の方をよく見て、どうすればうまく息を合わせて一緒にやれるのかをすごく考えながらやっていますね。
――距離感の見極めはなかなか難しそうです。
もちろん、「あ、メインMCの方とコメントがかぶってしまったな」「発言のタイミングが違った」など失敗をして密かに落ち込む日もあります。でも、人との距離感は経験で覚えていくしか方法がありません。失敗もしつつ、次に生かしていくことが大事だと思います。
思うような仕事ができないときも、腐らないことが大事

「会社でやりたいことができず悩んだ時期もありますが、長年組織にいてあらためて振り返ってみると、自分がやりたいことと、第三者が向いていると感じることは違う。会社での配属先というのは人事部や上司といったキャリアのある方々が適性を判断して与えてくれたものなので、まずはそこで頑張ってみることも大事だと思います」と真麻さん。
――ところで、真麻さんの就職活動についてうかがいたいのですが、テレビ局のアナウンサーを志望された理由は?
父が俳優だったので、人に何かを伝える、表現する仕事にはもともと興味がありました。では、具体的にどんな職業がいいかなと考えたときに、私は子どものころから絵本を声に出して読んだり、おいしい食べ物のことを自分の言葉で誰かに伝えるといったことが好きだったので、アナウンサーになりたいと思いました。
一方、父がずっと芸能界で仕事をしていて、子ども心にフリーランスの不安定さを感じていたので、できれば大きな会社で働きたいと考えていました。やってみたいと思う仕事と、「大きな会社で働きたい」という思いが交差したところが、テレビ局のアナウンサーだったんです。ただ、テレビ局のアナウンサーは応募者も多く、誰でもなれる職業ではないと覚悟していました。ですから、「アナウンサーになりたい」と明確に目標を決めた大学1年生のときから、各局のマスコミセミナーやアナウンススクールに通って知識や技術を学びました。大学1、2年生のほとんどの時間をアナウンスの勉強に費やした気がします。
――その成果が実って、2004年にフジテレビに入社されました。
内定をいただいたときは本当にうれしかったですし、120パーセントの努力をしてようやくアナウンサーになれたという自負もありました。ところが、入社後に待っていたのは、いきなりのバッシングでした。就職活動時には父が俳優であることを明かしていなかったのですが、世の中に知られたとたん、「ブサイクだ」「コネだ」とインターネットや雑誌でたたかれました。私の顔がフジテレビのアナウンサーにしては若干トリッキーだったせいかもしれません(笑)。今なら笑い話にできますが、当時は相当なショックを受けました。
入社後しばらくは、自分がやりたい番組を担当できなかったり、周りが自分よりも仕事に恵まれているように思えたりと、理想と現実のギャップに悩む日も多かったです。アナウンサーの仕事には表舞台に立つ業務のほかに、インタビューの聞き手で顔が映らなかったり、ナレーションで名前も出ない仕事もたくさんあります。入社2、3年目にそういう仕事が続いた時期があり、「私に回ってくるのは、誰がやってもいいような仕事ばかり」と落ち込み、本気で退職を考えたこともありました。そのときに励まされたのが、「誰がやってもいい仕事こそ一生懸命やりなさい。そうすれば、『最初は誰でもいいと思っていたけれど、真麻に頼んでよかった。次は真麻を指名しよう』ってなるから」という父の言葉です。
確かにそうだなと納得し、それからは、「誰かひとりでも視聴者の方や、その仕事に携わっている方がいれば、その方たちに応えたい」という思いでどの仕事にも一生懸命向き合いました。そのうちに、負のスパイラルから抜けて、いい仕事ができるようになっていったように思います。
また、そう思い直すことができたのは、先輩や同僚の影響もありました。フジテレビではテレビ番組の制作を担当していた方が人事部や総務部に配属されるといった結構大きな異動もあるんです。そのときに、最初は皆さん、どうしても「え!?」という反応をされるのですが、どの部署に行っても腐らないんですよ。その場で自分のできることを探して輝いて、会社を盛り上げていこうという姿勢の人がとても多く、私自身も自然と前向きな考えを持てました。独立した今も、いい会社で働かせていただいたなと感謝しています。
社会に出たら、誰しも多かれ少なかれ、理想と現実のギャップを感じるものです。どんな場所にいても、腐らないことが大事だと思いますね。
社会と手をつないで生きていくことの大切さを父に教えられた

バラエティー番組のイメージが強いが、フジテレビ時代はBSや報道番組でニュースを読む仕事を長く担当した。「きちんとニュースを読むという、アナウンサーとしての核となる部分があったからこそ、バラエティー番組でどんなイジられ方をしても気になりませんでしたし、このギャップこそが自分の強みだと思っていました」と笑顔で話す。
――2013年にフジテレビを退社し、独立されました。お仕事で周囲の人と関係性を構築していくうえで、会社員時代との違いを感じたり、戸惑ったりはしませんでしたか?
会社員時代は、私のキャラクターを番組制作のスタッフがよく知ってくれていて、「この役割は真麻に」という感じでお仕事の依頼があったので、自分に求められていることがわかりやすかったんです。ところが、フリーになってからは、初めて一緒にお仕事をする人がほとんどで、「真麻さんらしくお願いします」と言われたときに、その方が求めている私らしさというのは何だろうと悩むことが多かったです。天真爛漫に振舞っている私なのか、ニュースをきっちり読んでいたときの私なのか、それとも、二世タレントっぽい感じの私なのかと(笑)。
ですから、仕事が終わるたびに「あの場面で、あの発言はよかったのだろうか」「今日の感じで大丈夫だったのだろうか」と振り返り、求められているものに応えられているのかを探りながらやっていました。フリーになって2年間くらいは、フルスイングはしていたけれども、空振りも何回もあったなというふうに感じています。でも、月日を重ねるごとに、自分の立ち位置はこうなんだなとか、この番組で求められているキャラクターはこうなんだなということがわかるようになりました。
――さまざまな方とお仕事をされるなかで、この人はすごいと感じる方はいますか?
それはもう、全員がすごいです。芸人さんやタレントさんなど表に出ている方たちばかりでなく、構成作家さんや番組スタッフの方々であったり、職種を問わず、第一線で活躍されている方というのは理由がありますよね。そのすごさというのは、具体的なことというよりは、プロ意識の高さや周囲への細やかな配慮といった肌で感じるもの。具体例を挙げはじめたらキリがないほど、全員がプロフェッショナルな気持ちでひとつの番組を作っていると常々感じます。
――お父さまと共演されることもありますが、一緒にお仕事をされていてすごさを感じることは?
一緒に仕事をしてというよりは、幼少期に見た父親の仕事に対する姿勢は、今にして思えば、すごかったなと感じています。例えば、父は時代劇を演じてきたので、着物の着方や、立ち居振る舞いを身につけるために日本舞踊を習っていて、夜中までの撮影の後に朝までお稽古というようなことを日常的にやっていました。大変だっただろうなと思いますが、本人にとっては苦痛ではないんですよ。理由は、そうした準備をすることで、自分の演技や所作に自信がつき、より良いパフォーマンスを発揮できるという発想だから。父の、努力を苦にせず、当たり前のようにやっている姿というのは、本当にすごいなと思います。
――最後に、学生にメッセージを!
私自身が就職活動を経験して感じたのは、就職活動に正解はないということです。とりわけそう実感したのは、アナウンススクールに通っていたとき。お台場のレインボーブリッジの前で1分間のリポートをするという課題があり、その日がちょうどお台場の花火大会の日だったので、リポートの最後に「今日は花火大会があります。真っ白なレインボーブリッジがレインボー色に染まるかもしれませんね」というひと言を添えたんです。そうしたら、授業で講評をいただいた際に、ひとりの先生は「個性があるし、アクセントが効いていていいですね」とほめてくださり、別の先生は「学生なのに、ちょっと気の利いたことを言おうとしている感じが鼻について、あまり好きじゃない」とおっしゃったんです。
そのときに思ったのは、同じことを言っても、人によって評価は違う。ということは、就職活動でもどの採用担当者の方に当たるかで結果が左右され、自分ではどうしようもない部分も大きい。結局は縁と運とタイミングなんだなと。それならば、就職活動では嘘をつくことなく、等身大の自分で相手に向き合い、そのとき与えられた課題に対して純粋に思っていることを伝えようと考えて臨んだら、フッと採用していただけたような感覚があります。ですから、就職活動がうまくいかなくても落ち込み過ぎず、自分らしさを失わずにいていただければと願っています。
取材・文/泉 彩子 撮影/刑部友康
衣装協力/HEART CROSET